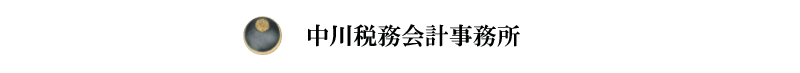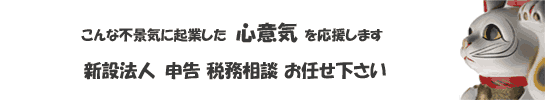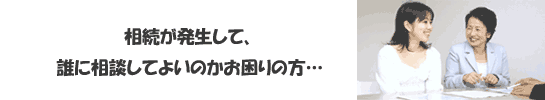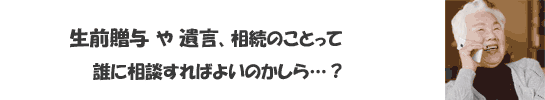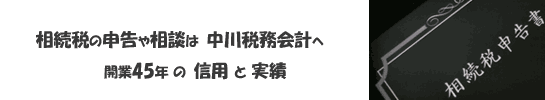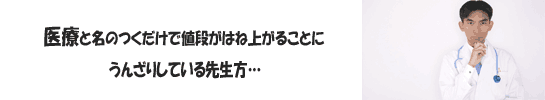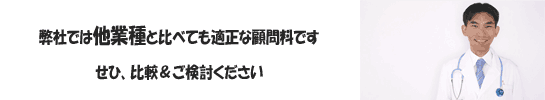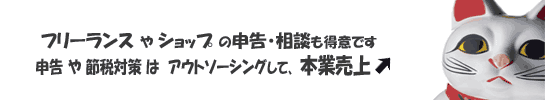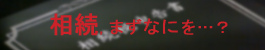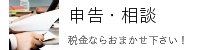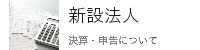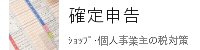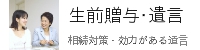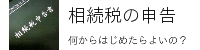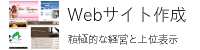相続税額は税理士によって変わります
相続税に関しては、私たち税理士からしても、年に1度申告が必要な会社の決算や確定申告などと違い、定期的に発生するものではありません。一口に税理士と言っても、得意分野があるのが実情です。相続税に関しては、その傾向が顕著で、過去の申告件数に幅があるのも事実です。経験と実績は、相続税額の決定に重要な要素を占める「財産の評価」や「税務調査対策」に差が出ます。また、相続税額以外にも、遺産分割協議も非常に重要です。遺産分割は、相続された方のその後の生活にも大きな影響を与えるため、相続税申告には、先々を見据えた的確な遺産分割や資産保全の面から考える事も重要となってきます。
評価で変わる相続税額
相続税を計算するときには、まず、だれが相続人なのかを確認することと、あわせて、相続する遺産の総額を把握します。このとき、遺産が全部、現金や預金ならば、金額を把握するのは簡単ですが、不動産や株がある場合、一度、評価して、現金に換算して遺産の総額を確認します。したがって、「財産の評価額の差」は「相続税額の差」となります。法人税や所得税は、誰が計算しても同じ結果になりますが、相続税は評価の方法しだいで税額が変わります。
たとえば、相続財産に土地がある場合、通常は路線価で価格を算定します。バブル期には、実勢価格が路線価をかなり上回っていましたが、最近では、路線価と実勢価格にはほとんど差がなくなってきました。